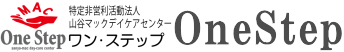会社の人間と飲んでも潰されるだけで旨い酒とは言えないと距離を置くようになったのがきっかけで、会社での居場所がなくなっていきました。結果、約2年勤めた会社を退職しました。この頃から「馬鹿馬鹿しい人間関係なんていらない」と強く感じるようになり、人を斜から見るのが強くなりました。「俺と同年代の奴はまだ遊んでて親のスネかじってんだから俺もまだいいやと」と自分勝手な言い訳をして毎日のようにパチンコへ行ったり飲み歩いたりして本気で仕事を探さないでいました。そんな時に新潟での季節社員の職を見つけ友人と行きました。「さすが新潟‼日本酒が旨い」と毎晩ビール500mlを3本と地酒のワンカップを最低5本は飲んでから寝る生活でした。翌日の仕事には行くものの、気持ち悪さと睡眠不足を堪えながらの作業だったので、人よりもペースが遅く雑にしか作業ができなくなっており、そのことで白い目で見られているのを気づかないフリをして過ごしていました。この頃にはもう「飲まない」という選択肢は無くなっていました。
期間満了で帰ってきても「少しのんびりしてから定職を探す」と両親に言ってはいたものの本気で探すつもりはなく、貯金が消えるまでそんなに時間がかかりませんでした。「そろそろ働くか」と面接を繰り返し、やっと見つけた仕事も2年と続きませんでした。その頃によく母親は「○○君に女の子が生まれた」や「○○さんが結婚した」など、どこの情報網を使ったらそんなに耳に入るんだ?と思うくらい私の友人達の話を聞かせてきました。今思えば、ちゃんとして欲しいと母親からの訴えだったかもしれませんが、当時の私は友人達と比較されているようで、だんだん家でも窮屈な思いをするようになりました。「家にいるからそんな話を聞かされるんだ、家にいなければ聞かずに済む」と思い沖縄や栃木などに逃げるように季節社員として何か月も家を空ける生活を何回も繰り返しました。
20代半ば、「酒が好きだから酒屋になろう」と安易な考えで酒類販売店に就職し、バイク通勤を許されました。それまであまり飲まなかったワインやウィスキーを「味を知らなきゃ客に勧められない」と店の商品を閉店後にバイト達と飲むようになり、毎晩飲酒運転をして帰るようになりました。ある時、バイトと飲んだ帰りバイクにまたがったまでは覚えているのですが、何故か起きると救命救急センターのベッドでいろいろな機材が私を取り囲まれていました。両手に点滴、胸には心拍数を測る機材、ベッド脇には尿の袋などがついた状態。ベッドの周りは透明のカーテンで覆われ、その外では給食当番のような恰好をした両親と弟と職場の上司が私を見ていました。
後で聞いた話によると、時速100キロくらいで電柱に突っ込み、3日間意識が戻らなかったらしく、医師には「覚悟はしておいてください」と言われたそうです。
そんな状態になったにもかかわらず「運が悪かった・少し飲みすぎたかな?」と反省する事はなく、その後2回も飲酒運転で事故を起こし、救命救急センターに運ばれました。